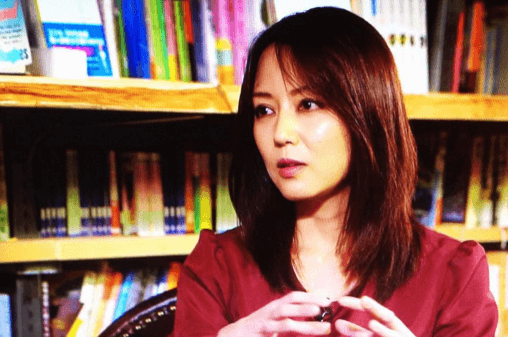
林修・世界の名著、今回のゲストは小説家の「うかみ綾乃」さん。
選んだ名著は谷崎潤一郎の「春琴抄」(1933)近代日本文学を代表する小説家です。
 (出典:www.museum.or.jp)
(出典:www.museum.or.jp)
番組冒頭から「今回はかつてないほど苦悶し、苦心し、苦悩しました」と言う林先生。
案の定?林先生は終始押され気味。うかみ綾乃さん独特の雰囲気と理解の深さが相まって、谷崎潤一郎の世界がより濃く感じられた放送となりました。
谷崎潤一郎「春琴抄」の物語と文体
美しくも残忍な盲目の三味線師匠「春琴」と、ひたすら彼女に尽くす奉公人の佐助。美しく壮絶な師弟愛を通して、マゾヒズムを超越した耽美主義を文豪・谷崎が描き出した名著である。
物語
9歳の時、病気で失明した大店(おおだな)のお嬢様・春琴。その直後から4つ年上の丁稚(でっち)佐助に身の回りの全てを世話させ、佐助は生涯を捧げることになる。そして春琴17歳の時、佐助との子を宿すが「春琴が命じたことに佐助が従う」という関係は変わらず続いていく。そしてある事件をきっかけに佐助は自らの目を突き、盲目になる。
文体について
うかみ綾乃さんは文体についてこのように語っていました。
うかみ綾乃と「春琴抄」の関係
うかみ綾乃さんが谷崎作品の中でも一番読み返してきたのが「春琴抄」。人生の時々で自分を測るためのバイブルのような作品だと言います。
そんなうかみ綾乃さんは「春琴抄」の捉えかたをこのように言っていました。
13歳で初めて読んだ時は、私もまだ子どもで分かってませんでしたね。「なんて究極の愛の物語なんだろう」「佐助のような下僕がいたら、自分だけの崇拝者がいたら人生どんなに楽であろうか」と思ったけど、それは甘かった。子どもでした。
20代、30代と読む度に考えは変化していったんですけど、13歳の自分が思い描いていた「愛」の形の延長線上に2人はいなかった。
ひと言で言うなら「佐助は恐い人」でした。春琴は佐助にさえ出会わなければ、もっと卒なく上手く生きることができる女だった。
またこのようにも言っています。(放送して良いのか?という夜の内容が含まれています。)
「余白」のある作品ですよね。余計な感情表現がないんです。わざと谷崎は想像させる幅を用意していると思うんですよね。最初の「春琴はなぜ盲目になったのか?」からずっと謎を作っていて、その余白が想像力を掻き立て、奥行きが深まるんです。その奥行が深ければ深いほどその根っこが自分の淫心に突き込んでくるんですよね。その淫心とか官能というものに目覚めた時から読み方が全然変わってきてしまいます。はは。
「春琴抄」はマゾヒズムなのか?
まずは、うかみ綾乃さんが選んだ一節です。
佐助は皆が熟睡するのを待って起き上がり布団を出したあとの押入の中で稽古をした。
これは主人である春琴が修行している三味線を、佐助が誰にも見られないように練習しているシーンです。
話は進んでいきます。
勿論爪弾き(つまびき)で撥(ばち)は使えなかった燈火(とうか)のない真っ暗なところで手さぐりで弾くのである。しかし佐助はその暗闇を少しも不便に感じなかった盲目の人は常にこう云う闇の中にいるこいさんも亦(また)此の闇の中で三味線を弾きなさるのだと思うと、自分も同じ暗黒世界に身を置くことが此の上もなく楽しかった
うかみ綾乃の解説
佐助にとって一番幸せで、また春琴をこの上なく感じたシーンは2つあります。一つは上記のシーン。この時は春琴のまとっている闇を自分も同じようにまとって、三味線の稽古をしています。もう一つは佐助が目を突くシーンです。
この時、佐助の中には「生身の春琴」はいません。ただ春琴と同じものを感じて一体化している、そのことが佐助にとって物凄い幸福だったんではないかと感じさせられます。
春琴は佐助がいない人生は考えられない状況に追い込まれた、そういう意味で佐助は究極に恐ろしい存在です。春琴が女性だから追い込まれたというよりも、「春琴という人間」だからこそ追い込まれてしまったと考えられます。
この小説はよくマゾヒズムという言葉で説明されますが、佐助はどちらかと言えば「究極のオナニスト」だという感じですよね。
佐助の本性が分かるシーンと解釈
ある時、何者かが春琴に熱湯を浴びせて火傷をおわせ、その美貌を無残な姿に変えてしまいます。春琴が見られるのを恐れたのと同じように、佐助もまた見ることを恐れました。
このシーンについてうかみ綾乃さんは次のような解釈をしています。
佐助は春琴でした。最初からずっと春琴になりたかったんです。春琴が望むことは自分が望むこと、一体化をずっと望んでいたんです。
うかみ綾乃の真骨頂!最も官能的だと感じたシーン
うかみ綾乃さんが最も官能的だと感じたのが「梅見の宴」のシーンです。林先生は「え?意味分かんないぞ?」という表情をしていましたが・・・。
では、まずは梅見のシーンの本文を。
滑稽なことは皆が庭園へ出て逍遥(しょうよう)した時佐助は春琴を梅花(ばいか)の間に導いてそろりそろり歩かせながら「ほれ、此処にも梅がござります」と一々老木の前に立ち止まり手を把って(とって)幹を撫でさせた凡そ(およそ)盲人は触覚を以って(もって)物の存在を確かめなければ得心がしないものであるから、花木の眺めを賞するにもそんな風にする習慣がついていたのであるが、
分かる人には分かるシーン
うかみ:この作品は谷崎演じる作家が二人のことを描いていくという体で進められますよね?でも、この作家は徹頭徹尾2人に対して辛辣で突き放した書き方をしているんですよね。
例えば、佐助が「どれだけ春琴が琴の名手で美しくて・・・」と感じている文章を残していても、作家は「いやぁ、でもね…」というような描き方もしています。それは2人が心を通わせ合っているシーンであるほど、2人を滑稽に愚かしく描いているように思うんです。
この梅見のシーンにしても、もっと2人にとって優しく温かく美しいシーンとして表現することはできたずです。でも、そうはしなかった。その上次のシーンでも周囲が2人を茶化すような場面になっています。
林修:それはなぜそう描かれたと思いますか?
うかみ:愛ってそういうものだからだと思います。「強すぎる愛」とか「行き過ぎた感情」っていうのは決して周りから美しいと言われるものではないですよね。時には嘲笑の的になることもあります。周りから理解されない。そういうたった2人の世界を浮き上がらせて描くことで、この2人の特殊性も浮きあがさせているんじゃないですか?
林修:今の話を聞いていて気がついたんですけど、この本の表紙って梅の絵になっていますね!これは加山又造さんていう有名な画家が装丁をされているという、今で言うと考えにくいものですけど・・・これ、分かる人には分かるってことなんですねぇ。何か今回は気分的にズタボロの回だなぁ・・・。
うかみ:又造さんと私には分かったってことですねっ。ふふふ。
2人が初めて肌を重ねた時の佐助の気持ちは?
この小説では2人がどのようにして初めて肌を重ねたのかが描かれていません。そのため「想像ではどう思いますか?」という質問を、うかみ綾乃さんが問いかけました。
林修:不要
林修:最初は「神聖なものを汚した冒涜感」としていましたが、うかみ先生の本の解釈を聞いているうちに「違うな」と思ったので変えます。普通の男女だと男のほうが求めますが、この2人の場合は佐助から求めることは考えにくい。
うかみ:苦行僧の愉悦
うかみ:私もそう思います。想像ですけど、絶対に春琴の方から「私を抱け」みたいに大雑把に命令して、佐助はアタフタしたでしょうね。この時も2人は目も合わさずに会話も交わさなかったと思います。
林修:究極の愛というか何というか・・・
うかみ:愛というよりは「同化」する物語ですよね。お互いエゴイズムの極地で、相手のためになんて何もない。相手の喜びは自分の喜び、自分の喜びは相手の喜びみたいに。もはや2人のエゴイズムがピタッとキレイに重なっている。小さい頃から癒着しちゃってるんですよね。
林修:もう、これは実際に読んでもらうしかないですよねぇ。
うかみ:そうですね。若いころからでもまず1回読んでもらえれば、その後の人生に面白みが増すんじゃないでしょうかね?ふふ。
林修:はは・・・(苦笑)
うかみ綾乃さんが記す、この本を表すひと言とは・・・。
「あなたは私よ」
林修:うわぁ、また強烈な・・・。これが春琴を指すのか、うかみさんを指すのか。その受け取り方で僕という人間が炙りだされるような・・。とにかく今回は全部ズタボロです。
↓番組使用は「梅の絵」が施された新潮文庫でした。

